頭痛外来とは
主に慢性的な頭痛に悩まされている方を対象としている外来になります。
一般的に大半の方は頭痛を経験したことはあるかと思いますが、この状態が長い間続いている、良くなったり悪くなったりをずっと繰り返しているとなれば、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
この場合、頭痛そのものが症状であるという一次性頭痛と何らかの原因疾患があって発症する二次性頭痛に分けられます。
なお後者(二次性頭痛)に関しては、緊急性が高く、生命に影響することもあるので要注意です。
頭痛がどうしても気になるという方は、速やかに頭痛外来をご受診ください。
頭痛を訴えて来院された患者さまは、まず一次性なのか二次性なのかを調べる必要があります。
診断をつけるにあたっては、問診をはじめ、神経学的検査(項部硬直、眼底検査、継ぎ足歩行 等)、画像検査(頭部CT、頭部MRI 等)を行い、一次性あるいは二次性のどちらかが判明するようになります。
一次性頭痛であれば、さらに丁寧な問診を行い、どのタイプの頭痛であるかを判定していきます。
二次性頭痛となれば、さらに血液検査や髄液検査等によって、原因疾患を特定していきます。
一次性頭痛とは
頭痛を引き起こす原因と考えられる疾患などはなく、生命に影響はないとされる頭痛が一次性頭痛です。
主な種類としては、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛があります。
【片頭痛】とは

脳にある血管が拡張することで発生する頭痛になります。
20~40代の女性に発症しやすく、男女比は1:4程度です。
これといった原因もなく発症することもありますが、飲酒、天候や気温の変化、睡眠不足、月経中などエストロゲンの分泌が変動している(女性のみ)、チョコや赤ワインを摂取する、ストレスから解放された等がきっかけになることもあります。
なお人によっては前兆が現れるとされ、その場合は頭痛発作の前に閃輝暗点(目の前が見えにくくなる)がみられるようになります(片頭痛の患者さまの3割程度)。
主な症状ですが、こめかみより側頭部にかけてズキズキと脈打つ痛みの頭痛(中等度~重度)に見舞われます。
頭痛以外にも嘔吐や吐き気、羞明(光を異常にまぶしく感じる)、音に対して過敏になるといったこともあります。
頭痛発作の持続時間としては半日~24時間程度で、頻度としては月に1回~ほぼ毎日と様々であり、最初は片側のみでも多くは両側で頭痛が起きるようになります。
治療について
頭痛発作時の治療では薬物療法として、トリプタン製剤がよく用いられます。
上記以外にもNSAIDsなどの鎮痛薬やエルゴタミン製剤などを使用することもあります。
少し難しい話ですが、頭蓋内組織に分布する三叉神経終末が刺激を受けると、カルシトニン遺伝子関連ぺプチド(CGRP: Calcitonin Gene-Related Peptide)、サブスタンスPなどを放出し、局所的な炎症、血管拡張が生じ、頭痛発作が引き起こされるという三叉神経血管説が考えられています。
そこで、2021年には片頭痛の発症に関与する物質であるCGRPをブロックすることで片頭痛を予防するCGRP関連製剤(エムガルティ®、アジョビ®、アイモビーク®)が使用開始となり、重篤な片頭痛発作の患者さまには非常に有効な治療が誕生しました。
また片頭痛の頻度が多ければ、予防薬として、抗うつ薬、抗てんかん薬、カルシウム拮抗薬等を使っていきます。
このほかにも片頭痛の発症リスクが高くなりそうな生活習慣(睡眠不足・過多睡眠、飲酒、疲労、ストレス 等)を控えていくようにもしていきます。
【緊張型頭痛】とは
一次性頭痛の中では、一番頻度が高い頭痛で、30代以上の世代から見受けられるようになります。
発症の原因については、現時点ではっきり特定していませんが、精神的もしくは身体的ストレスをはじめ、長時間のパソコン作業(うつむき姿勢)、運動不足、眼精疲労などによって、頭部を支える筋肉に緊張が生まれるようになって、緊張型頭痛は起きるのではないかといわれています。
よくみられる症状ですが、頭が締めつけられるような痛みや頭重感に見舞われ、脈を打つズキズキした痛みではありません。
頭痛の程度は軽度~中程度なので、日常生活に多大な影響が及ぶことはありませんが、頭痛自体は1日中続き、夕方の時間帯になると憎悪することが多いです。
なお緊張型頭痛は、頭痛の発作が数分~1週間程度持続するとされる反復性緊張型頭痛と頭痛発作が始まって数日から数ヵ月続くとされる慢性緊張型頭痛に分けられます。
診断をつけるにあたっては、問診や診察が中心となりますが、器質性疾患の可能性を除去するための検査として、頭部CTや頭部MRIによる検査を行うこともあります。
治療について
頭痛を引き起こす主な要因とされるストレスの除去を行うことが大切ですが、症状を抑えたいという場合は薬物療法による対症療法が検討されます。
この場合、鎮痛薬であるNSAIDs、首や肩のこりが強いとなれば、筋弛緩薬を用いることもあります。
さらに薬剤を使用しない方法(非薬物療法)として、ストレッチや認知行動療法などを行っていくことも効果的です。
このほか、症状を軽快させる方法として、入浴、身体を適度に動かす運動療法なども取り入れると頭部を支える筋肉の緊張が和らげるということもあります。
【群発頭痛】とは

有病率は0.01%(およそ1,000人に1人の割合)とされ、男女比は5:1と圧倒的に男性が罹患しやすいとされる一次性頭痛です。
主な症状ですが、左右どちらか片側の眼窩部からこめかみにかけて、眼がえぐられるのではないかと思うほど強い激痛に見舞われ、その状態というのは1時間程度続くとされています。
激しい頭痛以外にも、流涙、鼻水・鼻づまり、眼の充血なども現れるようになります。
この頭痛発作は1度始まると2週間~1ヵ月程度の間、1日の中のほぼ同時間帯に現れるようになり(群発期)、1年間に1~複数回程度の群発期が見受けられるようになります。
発症しやすい世代は20~40代で、男性の患者さまが圧倒的に多く、アルコールの多量飲酒や喫煙者、気圧の変化などがきっかけとなって起こりやすくなります。
なお頭痛発作の原因は完全に明らかとはなっていませんが、頭部の血管拡張が関係しているのではないかといわれています。
診断に関しては、医師による問診や診察によってつくこともありますが、器質的疾患の可能性の有無を調べるための検査として、頭部CTや頭部MRIによる画像検査を行うこともあります。
治療について
激しい頭痛発作がある場合は、酸素ボンベからの酸素吸入(100%)が行われるほか、薬物療法としてトリプタン製剤による皮下注射が行われます。
このほかにも予防対策として、群発期の間は禁煙、禁酒を行う、カルシウム拮抗薬を用いるといったこともあります。
二次性頭痛とは
何らかの原因疾患があって、それによる一症状として現れている頭痛のことを二次性頭痛といいます。
この場合、発症している病気によっては、生命に影響が及ぶこともありますので、速やかに問診、診察、検査(CT、MRI 等)を行い、診断がつけられた疾患に対する治療を行うことで、頭痛の症状が改善していくようになります。
二次性頭痛を引き起こす主な疾患の種類
脳腫瘍、くも膜下出血、髄膜炎、慢性硬膜下血種、緑内障、副鼻腔炎 など
めまい外来とは

主にめまいの症状を訴えている患者さまを対象とした外来になります。
一口にめまいといいましても、それこそ目がグルグル回ってしまうめまい(回転性めまい)もあれば、足元がフラフラして、地に足が付いていない状態となるめまい(浮動性めまい)のほか、さらに立ちくらみを感じるという場合もめまいに含まれます。
めまいの症状がある場合、内耳(三半規管、前庭 等)の障害によって起きるケースもあれば、何らかの脳疾患や血管疾患を発症することでみられることもあります。
当院は、脳神経に関係した医療機関なので、脳血管で起きたとされる病気によるめまいを中心に診療していきます。
脳疾患が原因のめまいというのは、中枢性めまいと呼ばれ、小脳や脳幹に障害が起きることで発症するようになります。
また、めまい以外にも、頭痛、嘔吐・吐き気、嚥下障害、構音障害、半身麻痺などの症状がみられることもあります。
障害の原因としては、主に脳梗塞や脳出血といった脳血管障害、てんかん、脳腫瘍、脳挫傷などの病気が挙げられ、生命に影響することも少なくありません。
このような場合、フワフワした感覚になる浮動性めまいがよくみられるとされています(回転性めまいは内耳の機能障害でよくみられる)が、なかには回転性めまいであっても脳疾患が原因ということもありますので、種類にこだわることなく、めまいによる異常を感じたら速やかに当院をご受診ください。
何らかの脳疾患によるめまいが疑われる場合は、まず問診や神経学的診察を行います。
さらに頭部CTや頭部MRIによる画像検査も実施し、必要があれば診断をつけるためのより専門的な検査なども行っていきます。
中枢性めまいがみられるとされる代表的な疾患
脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳腫瘍、脳炎、パーキンソン病、多発性硬化症、脊髄小脳変性症、頭部外傷(脳挫傷) など
もの忘れ外来とは
もの忘れとは、加齢による年相応の知的機能の衰えのことをいうのですが、これは自然な老化現象のひとつでもあります。
ただこのもの忘れというのは、認知症で見受けられる症状のひとつであるもの忘れと非常によく似ているので区別がつきにくいということがあります。

ただその忘れ方というのに実は違いがあります。
例えば、認知症の患者さまでは体験してきたことそのものを忘れてしまうのに対し、加齢による物忘れの方というのは、体験の一部のみ忘れているという特長があります。
具体的にいえば、朝食を食べていたのにも関わらず、そのこと自体を忘れてしまうのが認知症の患者さまです。
その一方で、朝食を食べていたことは覚えているものの、何を食べたかを忘れているというのが加齢による物忘れの特長です。
ただいずれにしても、その違いを一般の方々が見極めるのは難しいので、気になることがある、認知症を発症しているか不安という場合は、遠慮なく当院をご受診ください。
もの忘れ外来では、まずもの忘れ患者さまや同居するご家族さまに対する問診から始めていきます。
認知症が疑われるとなれば、その患者さまに対する認知機能検査(MMSE、HDS-R 等)を行います。
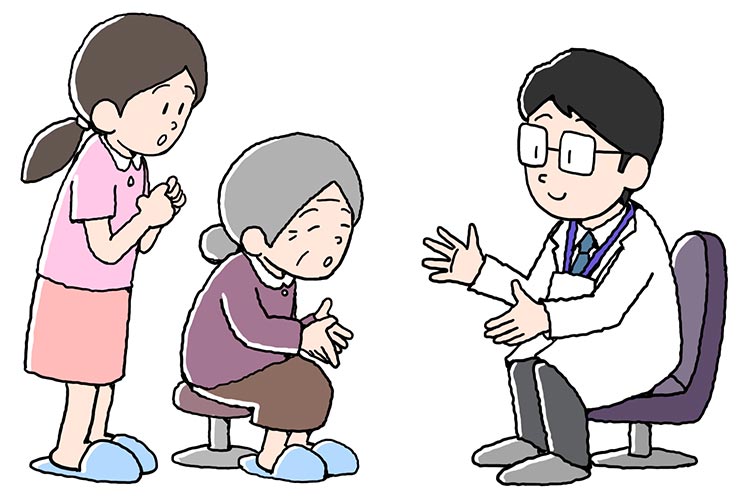
その結果、さらに異常があるとなれば、各々の認知症でみられるとされる特長的な症状の有無であったり、画像検査(CT、MRI、SPECT 等)を行ったりして、総合的に判断し、診断をつけていきます。
以下の症状に心当たりがあれば、一度当院をご受診ください
- 約束したことをよくすっぽかしてしまう
- 常に行く場所であっても道に迷うようになった
- 忘れ物をしたという自覚がない
- 身だしなみに気をつかわなくなった
- 金銭の管理をすることが困難になっている
- 日時や季節をよく間違える など
